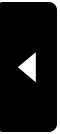佐藤洋子スケジュール
佐藤洋子はこちらで占断鑑定をおこなっています。
対面鑑定、電話、スカイプ鑑定ともに、年中無休で、佐藤洋子研究室にて。

占断鑑定をご希望の方は、お電話(054-246-3507)
メールはこちらにて (kabbalah1@air.ocn.ne.jp)お問い合わせください。
ホームページはこちらへ http://sato-yoko-lab.com/
佐藤洋子研究室鑑定料金
【静岡】カバラに興味があるならカバラの女王!佐藤 洋子先生を知らずにはいられない | 占いマガジン ウラッテ
占いマガジン ウラッテ
【静岡】カバラに興味があるならカバラの女王!佐藤 洋子先生を知らずにはいられない | 対面占い・電話占いガイドMy占い
対面占い・電話占いガイドMy占い
佐藤洋子はこちらで占断鑑定をおこなっています。
対面鑑定、電話、スカイプ鑑定ともに、年中無休で、佐藤洋子研究室にて。

占断鑑定をご希望の方は、お電話(054-246-3507)
メールはこちらにて (kabbalah1@air.ocn.ne.jp)お問い合わせください。
ホームページはこちらへ http://sato-yoko-lab.com/
佐藤洋子研究室鑑定料金
【静岡】カバラに興味があるならカバラの女王!佐藤 洋子先生を知らずにはいられない | 占いマガジン ウラッテ
占いマガジン ウラッテ
【静岡】カバラに興味があるならカバラの女王!佐藤 洋子先生を知らずにはいられない | 対面占い・電話占いガイドMy占い
対面占い・電話占いガイドMy占い
2014年12月13日
クリスマスフェスタでお正月飾り作り
 今日から、ツインメッセで開かれている、ホビーのまち静岡 クリスマスフェスタに来ています。
今日から、ツインメッセで開かれている、ホビーのまち静岡 クリスマスフェスタに来ています。アールブリエさんの、体験コーナーで、お正月飾りを作りました。
アーティフィシャルフラワーを使って、洋風な注連縄飾りです。
私は、紫色が好きなので、こんな感じに仕上げました。
小さな女の子から、年配の方まで、みんな、夢中で、作っていました。
楽しかったです!
2014年12月12日
紬デビュー、着付け編!
 着物井越さんの着付け教室に通っています。
着物井越さんの着付け教室に通っています。今日は、仕立てたばかりの紬を着ました。
絹の垂れ物と違って、着やすい印象です。
今月20日は、浮月楼さんで、着物パーティ。
着付け教室の生徒さんたちの、発表会でもあります。
あと、三回の着付け教室で、帯を完璧に覚えます。
頑張ります!
2014年12月04日
2014年11月28日
2014年11月26日
ライブ、始まりました!
 ロック喫茶、マキタさんとミッチャンとこに来ています。
ロック喫茶、マキタさんとミッチャンとこに来ています。佐藤慎哉さん、サトシンさんの方が分かりやすいかな?の、ライブが、始まりました。
私は、タロット占い師として、マキタさんのお店の一角にいます。
楽しい夜の始まりです!
2014年11月01日
2014年10月28日
着付けにトライ中です!
 着物井越さんの着付け教室で、着付けにトライ中です!
着物井越さんの着付け教室で、着付けにトライ中です!だいぶ、形になって来ました。
お着物を自分で、着ることが出来るようになると、また、バージョンアップした私になれそう!
しっかりマスターしますね!
2014年10月28日
2014年10月27日
着物井越さんで、お仕立て直し


着物井越さんで、祖母から、譲り受けた古い着物を、仕立て直して、綿入れ半纏にしていただくことにしました。
着物って、祖母が明治時代に着ていた、そのものを、譲り受けて、この平成の時代に、着れてしまうところが、すごいですよね?
祖母が自分で、縫ったお着物なので、それを仕立て直して、私が着させていただくって、なんだか、とっても幸せな気持ち。
この冬は、いろいろな意味で、暖かく過ごせそうです。
2014年09月21日
映画「舞妓はレディ」拝見しました。
 一昨日、母とともに、映画「舞妓はレディ」を拝見してきました。
一昨日、母とともに、映画「舞妓はレディ」を拝見してきました。この映画、主人公の女の子が、願いを成就させて、お客様の前で舞を踊るシーンで、私の篠笛の師匠・藤舎理生先生が、篠笛を吹いていらっしゃいます。
ですから、ぜひ、拝見したいと、前々から思っていました。
そして、スケジュールを調整して、やっとで見つけた、映画鑑賞日が、一昨日でした。
ネタバレにならないよう、ストーリーについては、あまり書かないようにしますね。
ただ、タイトルでもわかるように、この映画、オードリー・ヘップバーンの「マイ・フェア・レディ」のオマージュになっています。
「マイ・フェア・レディ」でも、言語学者の教授が出てきましたが、この作品でも、それらしき人物が・・・。
いけない、いけない、ネタバレ禁止ですね。
私個人の興味は、お着物を素敵に着こなしている女性にありますので、この作品には、大満足でした。
さまざまなシーンで、登場人物が、粋にお着物を着こなしているのは、さすが、という感じです。
ただ、ミュージカル仕立ての作品で、劇中、役者さんが、(脈絡はあるのですが)突然、歌いだすのが、ちょっと・・・という感じがしました。
私は、もともと、ミュージカル鑑賞を、あまりしたことがないので、そんな風に思ったのだと思います。
この映画で、舞妓さんや芸子さんについて、「所詮、お酒の席で、お客の相手をする水商売の女性だ」と、ある登場人物が述べていますが、そいう冷めた視点を加えることって大事だなと思いました。
舞妓礼賛の映画ではないところが、良いなと思いました。
でも、主人公の女の子、かわいかったです。
登場人物の中では、富司純子さんが、すっきり着物を着こなしていらっしゃって、素敵だなぁと思いました。
この映画、お勧めです。
ぜひ、ご鑑賞あれ!
それでは、また、お会いしましょうね!
佐藤洋子研究室のホームページはこちらです。
2014年09月17日
着付け教室に通っています。

着物井越さんの、着付け教室に通っています。
この画像は、夏に、東京で開催された、篠笛のおさらい会のリハーサル、下ざらい会に出席するために、着つけてもらった、浴衣姿です。
そう、私は、今年一月から、篠笛のお稽古を始めました。
そして、ほどなくして、お師匠さんから小袱紗(こふくさ)を用意しなさいと言われたのです。
呉服屋さんを回って、探したことを、、以前のブログで書きました。
そして、どの呉服屋さんにも、小袱紗はなく、たった一軒、井越さんだけが、小袱紗のありそうなお店の情報を、私に教えてくださいました。
小袱紗が茶道具であること、茶道具専門店が、静岡にあることを教えてくださり、そのお店・いとおさんのお店の地図を、プリントアウトして、渡してくださったのが、今思うと、井越さんにおける、私の現在の担当のSさんでした。
そのとき、私は思ったのです。
もし、今後、お着物が必要なときが来たら、井越さんにお世話になろうと。
そして、そのときは来ました。
篠笛のおさらい会(今年の夏でした)に出席するために、絽の着物をあつらえる必要が発生したのです。
迷わず、井越さんにお電話し、翌日、母とともにお店に伺って、反物から選んで、色無地の一つ紋の絽の着物を、作っていただきました。
そして、出来上がった着物を、着つけていただいて、無事、おさらい会を終えることができたのが、今年の8月3日のことでした。
9月から、井越さんで、着物の着付け教室が始まると聞いて、申込みを即、したのは言うまでもありません。
昨日で三回、習いました。
補正着を作った、第一回。
浴衣の着付けを習った第二回。
そして、昨日は、長じゅばんを着て、小紋の着物を着るところまで、習いました。
帯はまだです。
長じゅばんと絹のさらさらした着物を着るのって、結構、大変です。
合わせの小紋を、このお教室のために、作らせていただいた私ですが、先生に、「お教室で着るには、着物が上等すぎる」と指摘されてしまいました。
なので、もしかすると、この秋、紬(つむぎ)を作るかもしれません。
紬は普段着ですからね。
着物を自分で着ることができるようになって、日本人として恥ずかしくない振る舞いができるようになれたら、本当に素敵だと思います。
頑張ります!
それでは、また、ブログでお会いしましょう。
佐藤洋子研究室のホームページはこちらです。
2014年09月08日
和太鼓の発表会を拝見しました。
 知り合いの方が、和太鼓を趣味にされています。
知り合いの方が、和太鼓を趣味にされています。それで、その方が出演される、和太鼓の発表会のチケットをいただき、母とともに拝見してきました。
迫力ですね~!
ズンズンっと、お腹に響く感じです。
そして、和太鼓を演奏される方々の、かっこよいことと言ったら!
粋、というのかな?
祭り半纏を着こなして、力強く、和太鼓を叩いていらっしゃる姿、惚れ惚れしました。
男性だけでなく、女性の出演者の姿にも、惚れ惚れでしたよ。
私は、篠笛をお稽古していますので、動と言うより静の世界です。
もちろん、篠笛の曲にも、躍動的なものはありますが・・・。
いわば、対局に位置する感じの、和太鼓の世界に触れて、大いに触発されました。
チケットをくださったSさんに、感謝です!
それでは、また、ブログでお会いしましょう!
佐藤洋子研究室のホームページはこちらです。
2014年08月05日
篠笛、おさらい会の模様です。

篠笛のおさらい会で、私は、一番、若い弟子であることもあって、自分の写真をどなたかに撮っていただくということは、お願いしませんでした。
facebookで、師匠の藤舎理生先生のお友達の方(Tenshin Hanさま)が、この画像をアップしてくださっていました。
facebook上では、シェアさせていただきましたが、ブログでもご紹介させていただきたく、このようにアップさせていただきました。
2014年08月04日
篠笛のおさらい会に参加しました。
 今年の一月から、篠笛のお稽古を始めた私です。
今年の一月から、篠笛のお稽古を始めた私です。篠笛を手にして、半年余りになりますが、先輩弟子さんたちに交じって、藤舎理生先生の門下生として、おさらい会・理生の会~夏響~に参加させていただきました。
場所は、東京・神楽坂のうなぎ料理の老舗・志満金さん。
お着物で、新幹線に乗り、おさらい会に参加して、お着物のまま、再び新幹線に乗り、帰ってきました。
着付けは、お仕度を整えた呉服店の方にお願いしました。
何から何まで、初めてのことでした。
そもそも、篠笛を本格的にならって、半年余りで、先輩弟子さんに交じって、おさらい会に参加させていただくこと自体、大変、ありがたいことです。
しかも、会の後半では、会主の藤舎理生先生と、「桜」の二重奏をさせていただきました。
わたしが主旋律を吹き、二番からは、理生先生が、二重奏にしてくださったのです。

また、着物について、本格的に学んでみようと思ったのも、このおさらい会に、絽の着物が必要になったからです。
必要は、なんとかの母とやら・・・。
私は、この秋から、おしたくを整えてくれた呉服店の着付け教室に通います。
そのため、訪問着をひとつ、仕立てていただくつもりです。
「お稽古着にとどまらない、良いお品をお作り頂きます」と、おっしゃる呉服店の方々。
心強いですね。
今回のおさらい会に際し、会主の藤舎理生先生はもちろん、したさらい会(リハーサル)に、ご一緒させていただいた先輩弟子さん方、そして、お着物を仕立てたり、着つけてくださったりした、呉服店の皆様と、応援してくださる方々に恵まれ、本当に幸せなことでした。
この経験を、ぜひ、本業の仕事に生かすべく、感覚を研ぎ澄まそうと思います。
これからも、篠笛のお稽古、そして、お着物の着付け、しっかり学びます。
それでは、また、ブログでお会いしましょう!
佐藤洋子研究室のホームページはこちらです。
追伸です。
ダイエットも頑張りますね(^^;)
2014年07月19日
篠笛、稽古中です!
鑑定室で、仕事の合間に、篠笛を稽古しています。
実は、8月3日の日曜日に、私の師匠である藤舎理生先生の門下生の、おさらい会「笛 理生の会~夏響~」が、東京・神楽坂であるのです。
それで、現在、猛稽古中というわけです。
私は、門下生の中で、一番、若い弟子になります。
入門して半年あまりで、おさらい会に出させていただけることになりました。
演奏する曲は、長唄「宵は待ち」と、「さくら」です。
夏のおさらい会なので、絽の着物をあつらえ、準備を整えてきました。
しかし、なにより、笛の演奏がメイン。
初めは、おぼつかなかった、笛の音も、何度も、何度も、稽古しているうちに、なんとか、曲に聞こえるようになってきました。
もっと、もっと、稽古に精進して、良い音を出して、情感豊かに演奏できるようになりたいです。
それでは、また、ブログで、お会いしましょう。
佐藤洋子研究室のホームページはこちらです。
2014年06月16日
三島に来ています

三嶋大社にお詣りするために、三島に来ています。
画像は、三嶋大社に至る、水辺の参道です。
三嶋大社には、良いお水があると聞いて、今朝、いただいてきました。
昨日から、宿泊しているホテルからは、歩いて約20分の距離で、気持ちよく歩いて来ました。
早朝のお宮は、清々しく、お詣りして良かったなぁと、思いました。
ただ、早朝ゆえに、名物の福太郎餅のお店があいていなくて、残念でした。
これから、ホテルをチェックアウトしたら、三嶋大社に向かいます。
お土産を買って、帰ります。
では、また、ブログで、おあいしましょう。
2014年06月03日
篠笛、稽古しています。
 篠笛を習い始めて半年になります。
篠笛を習い始めて半年になります。今年のおさらい会は、東京の神楽坂で行われます。
絽の着物を着て参加するように言われました。
先日、母とともに、呉服屋さんで反物から選んで、無地の一つ紋の絽の着物をあつらえてもらうよう頼んできました。
さて、いでたちの準備は整いましたが、肝心の笛の腕前が、今のままではいけません。
なので、毎日、篠笛の稽古をしています。
最初は、息継ぎがうまくいかず、とぎれとぎれの演奏になり、とても楽曲に聴こえませんでした。
でも、毎日、篠笛を吹いていると、さすがに、曲らしくなってくるものですね。
まだまだなんですが、母曰く、「ずいぶん、良くなってきたよ」とのこと。
頑張ります!
篠笛は趣味と言うことになるのですが、実は、本業の占いに、良い影響がありそうなので、始めました。
と言いますのは、笛の音に、その場の気を浄める働きがあるからです。
もちろん、そういった浄めの音色を出せるようになるには、研鑽が必要ですが、場を浄められるような音色を目指して精進することは、占い師である私にとって、良いことだと思います。
なので、毎日、篠笛をお稽古しながら、より高い波動を持った占い師になるための修行をしている気持ちでいます。
良い音色が出せた日は、とても気持ちが良いですね。
精進しようと思います。
それでは、今夜も、スカイプ鑑定の時間が迫ってまいりましたので、この辺で。
また、ブログでお会いしましょう!
佐藤洋子研究室のホームページはこちらです。
2014年03月23日
HACO MARCHE、お邪魔しました!
 うつわ 暮らしの道具 テクラさんより、ご招待いただき、参加を予定していた、イベント、HACO MARCHE。
うつわ 暮らしの道具 テクラさんより、ご招待いただき、参加を予定していた、イベント、HACO MARCHE。今回のテーマ、“日本の馨り、春の香り“にふさわしく、美味しそうな匂いがしている会場でしたね。
私は、お昼を食べてから、会場に向かいましたので、残念ながら、ベジブロススープも、バーニャカウダも、いただけませんでした。
でも、とっても活気に満ちた会場で、見ていて、良いな、と思いました。
割と、早くに帰ってきてしまったのは、顔見知りの方を発見出来なかったからと、母に何か、美味しいものを、買って帰りたかったからです。
会場の食べものに、魅力は感じたのですが、結局、何も買わずに、帰路につきました。
母には、米八の三色おこわのお弁当と、スイーツを、松坂屋で買いました。
美味しいと、言ってくれるかな?
2014年02月20日
篠笛、稽古中です。
毎日、篠笛に触って、吹くようにしています。
先輩のお弟子さんが、毎日、とにかく、笛にさわることだよ、と教えてくださったので。
触ると、吹きたくなってしまいますから、毎日、吹くことになるのですね。
「さくら、さくら」を習い、曲がりなりにも、篠笛で、曲を奏でる第一歩を踏み出した私。
師匠である、藤舎理生先生の、三味線に合わせて、長唄を奏でるまでになるには、どれほどの道のりでしょうか?
先輩のお弟子さんのお稽古を拝見させていただいて、能管のお稽古などに接すると、ほんと、すごい迫力です。
能管とは、読んで字のごとく、お能のときに奏でる笛のこと。
高い、ピョオ~っという響きが特徴です。
いつか、私も、能管のお稽古ができるようになりたいな、と夢は膨らみます。
まずは、「さくら、さくら」を、なめらかに吹けるようにならなくちゃ、ですけど。
篠笛の楽譜は、数字の繋がりなんですよ。
運指表(うんしひょう)をもとに、穴のふさぎ方と数字が対応していますので。
さあ、「さくら、さくら」の復習から始めましょう!
それでは、また、ブログでお会いしましょうね!
佐藤洋子研究室のホームページはこちらです。
2014年01月15日
小袱紗(こふくさ)を購入しました。
なので、初稽古の後、私は、呉服屋さんを何軒かまわって、小袱紗を探しました。
しかし、ふつうの袱紗はあるのですが、小袱紗は、置いてあるお店がありませんでした。
ある呉服屋さんの店員さんが、お茶道具のお店なら、あるかもしれない、ということをおっしゃり、静岡市にあるお茶道具のお店を紹介してくださいました。
そして、翌日、そのお茶道具のお店・いとおさんに電話し、小袱紗の存在を確かめたのち、実際にお店にお邪魔して、求めたのが、画像の小袱紗です。
絵柄は、宝尽くし。
やや、お値段が高かったのは、宝尽くしの絵柄を織り込んであるからでしょうか?
そのお店には、さすがに、さまざまな絵柄の小袱紗がおいてあり、選んでいるとき、とても楽しかったです。
篠笛とともに、一生使うものなので、お金を出し惜しみせず、良いものを選びました。
ちなみに、小袱紗は、通常、お茶席で、お茶碗を運ぶ際、下に添えて使うとのことでした。
もし、時間に余裕ができたら、お茶も習いたいな、という気持ちが心をよぎりました。
でも、まずは、篠笛をまともにふけるようになるのが、先ですね。
毎日、習った三音を、吹いている私です。
だんだん、息が長く続くようになってきました。
良い音が出ると、部屋の空気が清められたような、すがすがしさがあります。
夕べは長唄「吉原雀」を聴きながら、休みましたが、歌詞を読みながら聴くと、いっそう、良くわかります。
とても、粋な感じの歌詞でした。
どうも、篠笛を習うということは、その「粋」という感覚を体感し、体現することも目的の一つなのかも、と思います。
まだまだ、その域には近づけませんが、一歩一歩、進んでいきたいと思います。
それでは、また、ブログでお会いしましょう!
佐藤洋子研究室のホームページはこちらです。

 日本茶の喫茶店、一茶で、静岡茶をいただいています。
日本茶の喫茶店、一茶で、静岡茶をいただいています。
 夕食の後は、少し歩いたところにある、喫茶一茶にて、静岡茶を満喫します。
夕食の後は、少し歩いたところにある、喫茶一茶にて、静岡茶を満喫します。 着物井越さんで、正絹の紬を作ることになりました。
着物井越さんで、正絹の紬を作ることになりました。